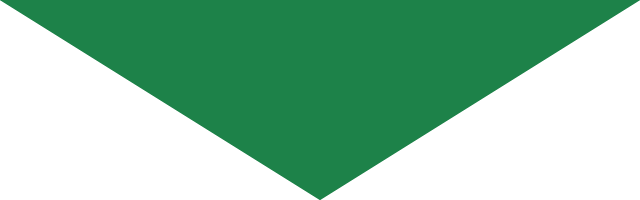【ケース1】令和6年中に扶養親族が増えた場合

令和5年中の扶養親族数 2名
①令和6年分推計所得税額 5万円
②所得税分定額減税可能額 6万円
③令和6年度個人住民税所得割額 7万円
④個人住民税定額減税可能額(※)2万円
②ー①=1万円
④ー③=0円
⑤当初調整給付の額(昨年支給分)1万円
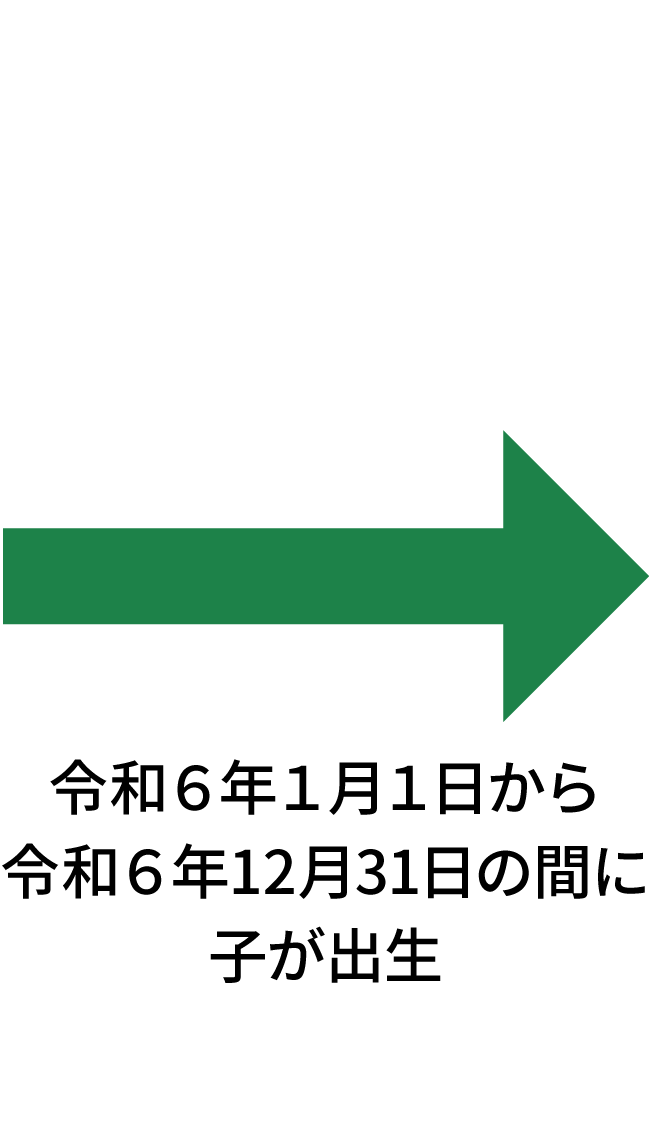
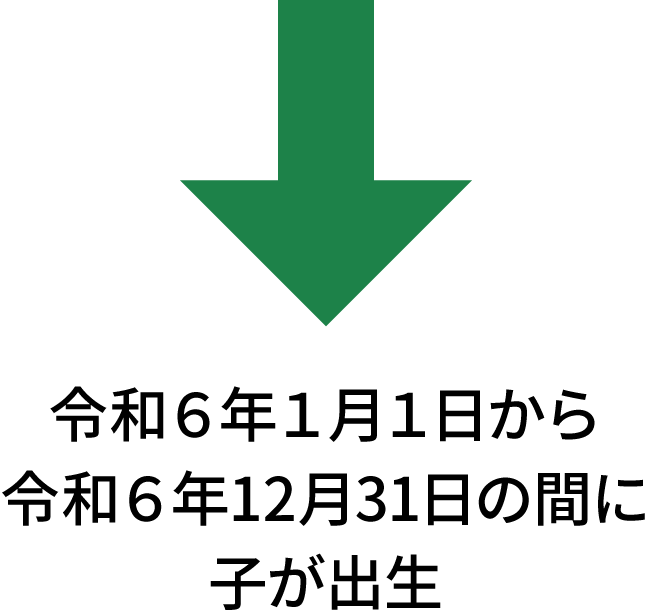

令和6年中の扶養親族数 2名
⑥令和6年分所得税額 5万円
⑦所得税分定額減税可能額 9万円
⑧令和6年度個人住民税所得割額 7万円
⑨個人住民税分定額減税可能額(※)2万円
⑦ー⑥=4万円
⑨ー⑧=0円
⑩不足額給付時所要額 4万円
令和6年度個人住民税分定額減税可能額は令和5年12月31日時点の扶養親族数から算出
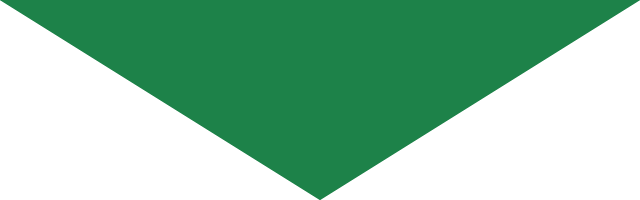
⑩4万円―⑤1万円=3万円
差額の3万円を不足額給付として給付
【ケース2】令和5年の所得と比べて令和6年の所得が減少したため「令和6年分推計所得税額」より「令和6年所得税額」が下回る場合
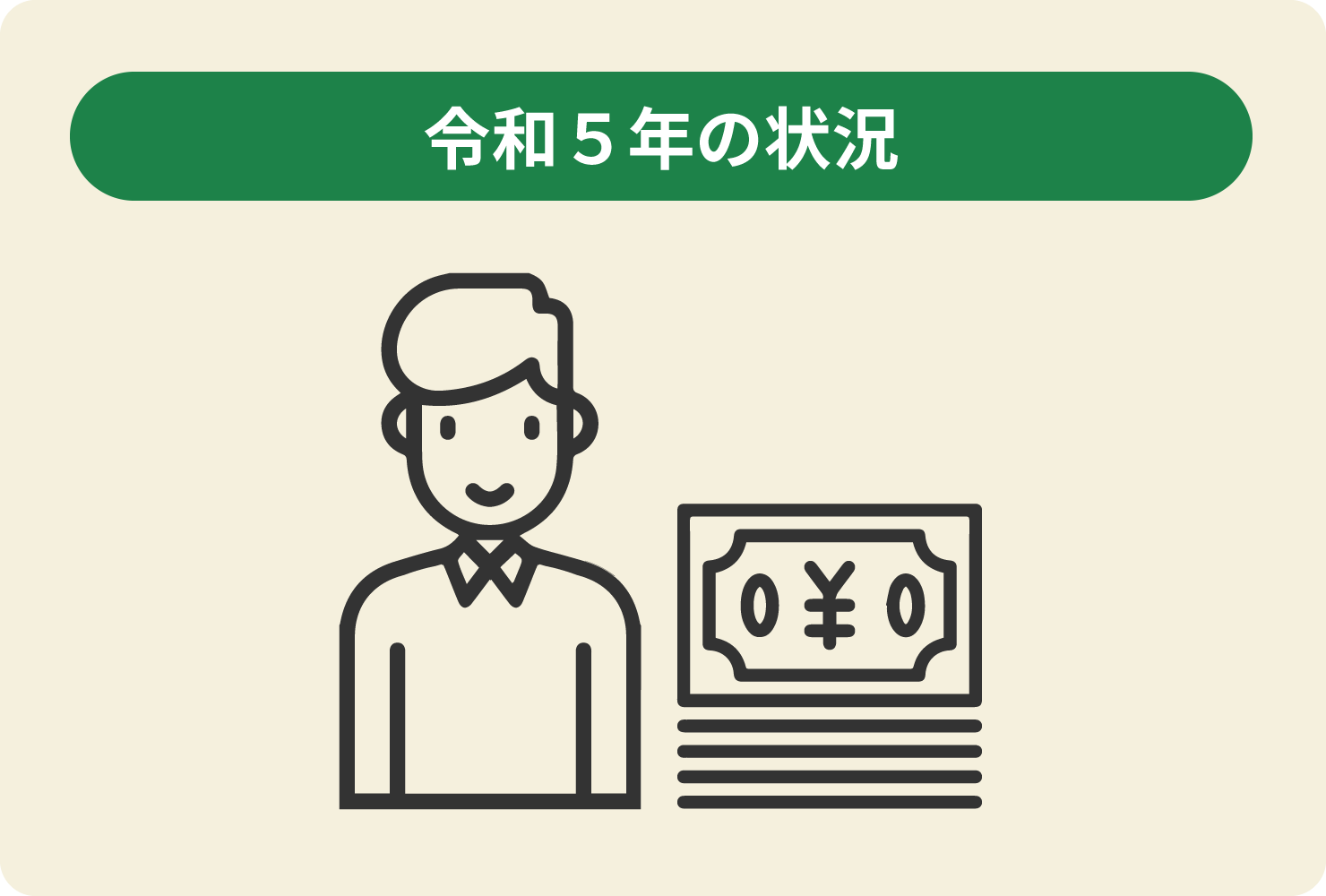
①令和6年分推計所得税額:2万円
②所得税分定額減税可能額:3万円
③令和6年度個人住民税所得割額:3万円
④個人住民税分定額減税可能額:1万円
②ー①=1万円
④ー③=0円
⑤当初調整給付の額(昨年支給分)1万円
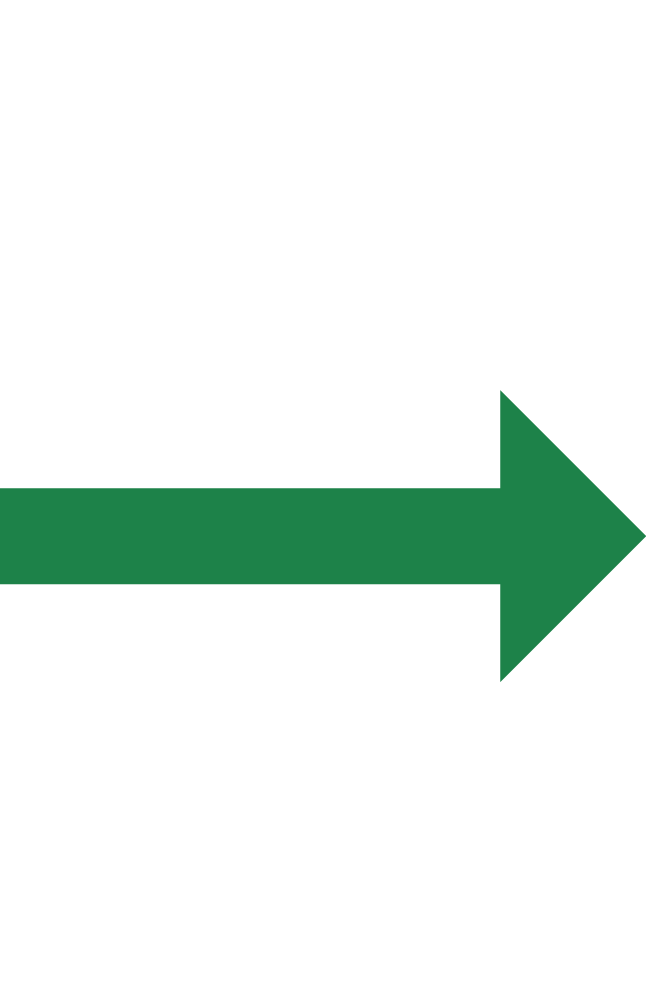
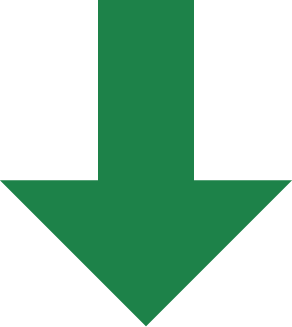
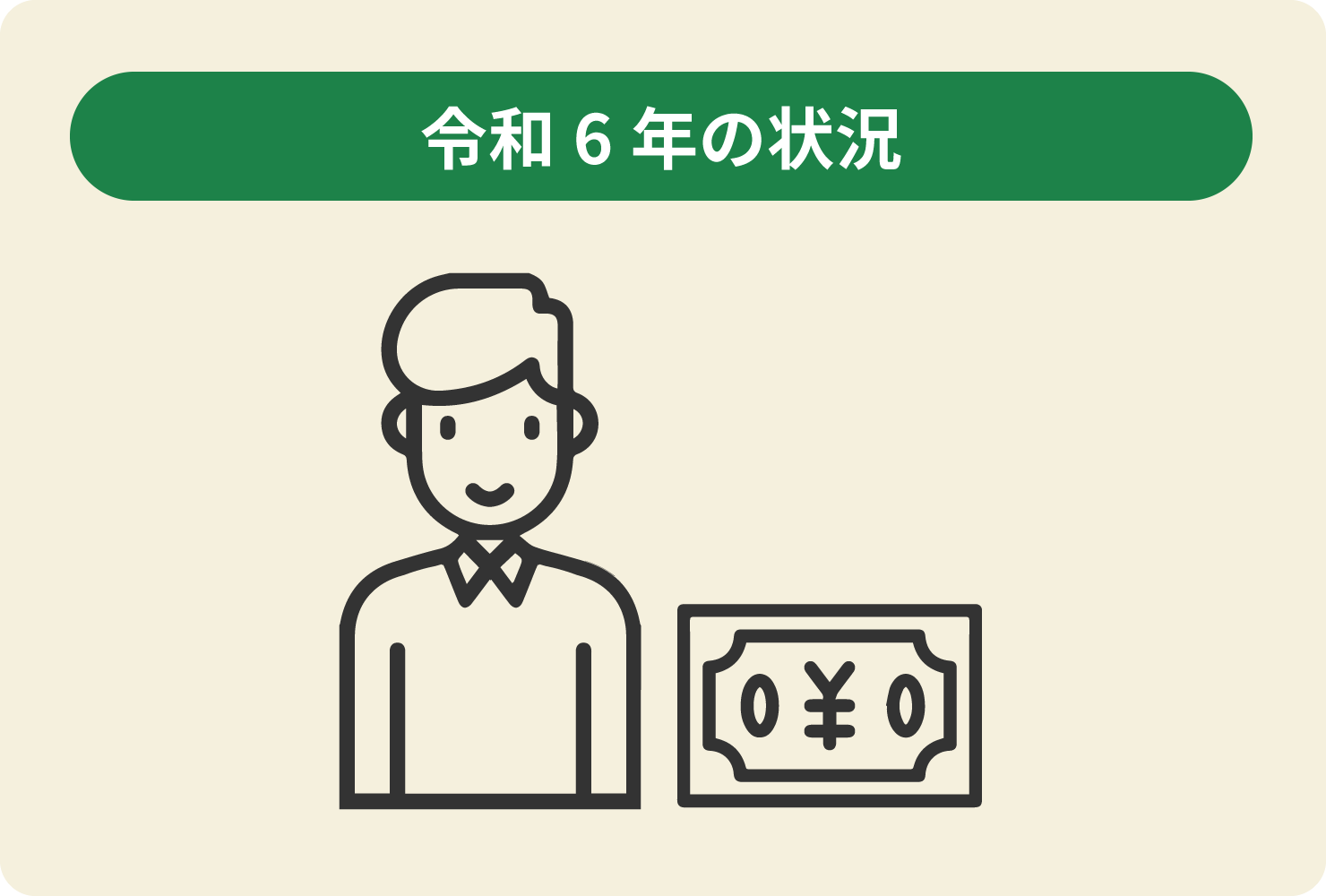
⑥令和6年分所得税額:1万円
⑦所得税分定額減税可能額:3万円
⑧令和6年度個人住民税所得割額:3万円
⑨個人住民税分定額減税可能額:1万円
⑦ー⑥=2万円
⑨ー⑧=0円
⑩不足額給付時所要額 2万円
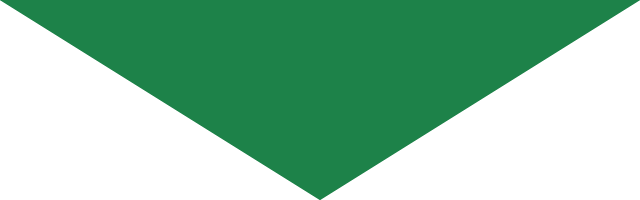
⑩2万円ー⑤1万円=1万円
差額の1万円を不足額給付として給付
【ケース3】父・子(納税者)・子の妻(納税者の被扶養者)の世帯公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税、住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である子と同居している場合

父(年金収入 165万円、非課税)
- 住民税、所得税ともに課されない
➡本人(父)は定額減税対象外 - 年金収入158万円(合計所得金額48万円)を超えている
➡子の定額減税においても扶養親族等とならない
子(納税者)
- 定額減税の対象
令和6年度個人住民税 1万円×2名(本人と妻)=2万円
令和6年分所得税 3万円×2名(本人と妻)=6万円
妻(収入なし、非課税)
- 住民税、所得税ともに課されない
➡本人(子の妻)は定額減税対象外 - 子の定額減税において扶養親族等となる
納税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税給付等)の対象外
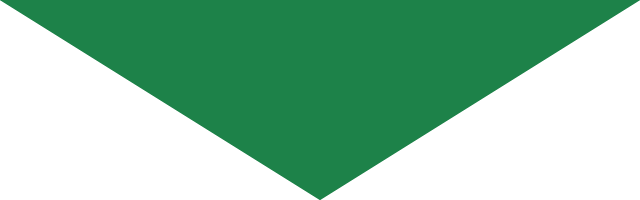
【ケース4】夫(個人事業主)・妻(専従者)の世帯納税者である夫の個人商店を手伝う専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合

夫(個人事業主、納税者)
- 定額減税の対象
令和6年度個人住民税 1万円×1名(本人)=1万円
令和6年分所得税 3万円×1名(本人)=3万円
妻(夫の専従者、給与収入50万円、非課税)
- 住民税、所得税ともに課されない
➡本人(妻)は定額減税対象外 - 専従者 *税制上、専従者は、所得に関わらず扶養親族には該当しないとされている。
➡夫の定額減税においても扶養親族等とならない
納税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税給付等)の対象外